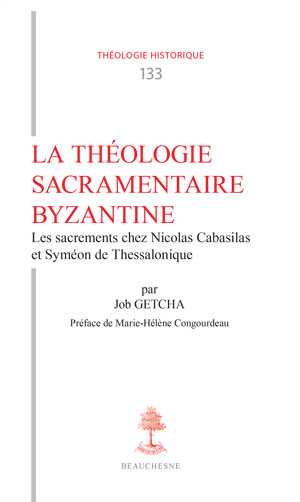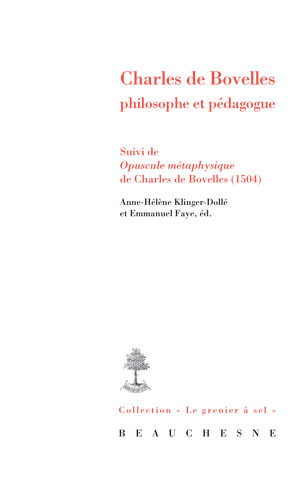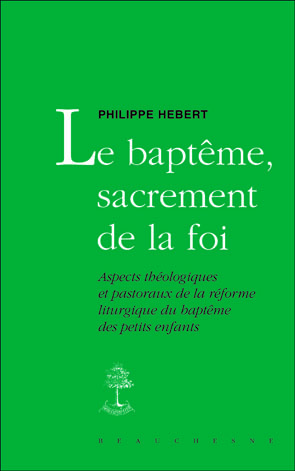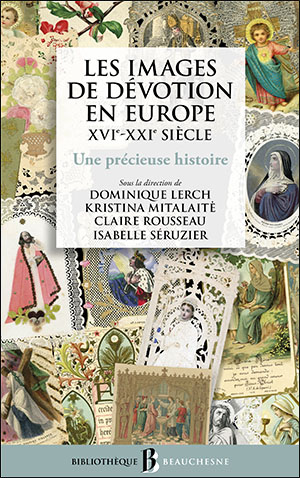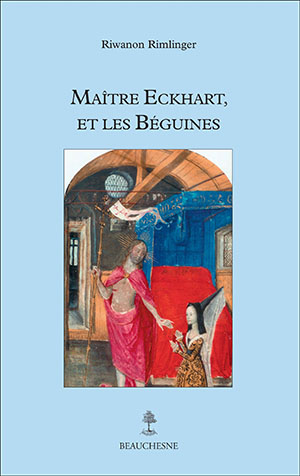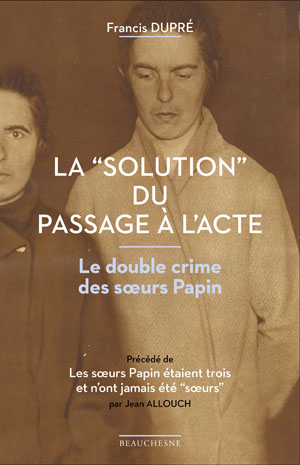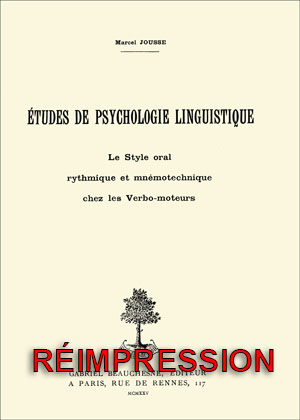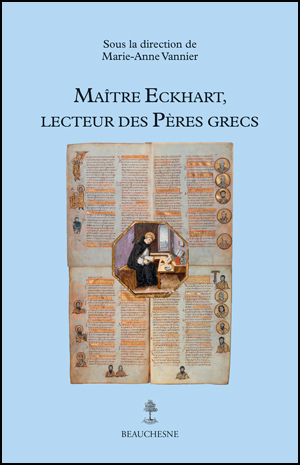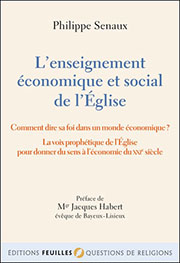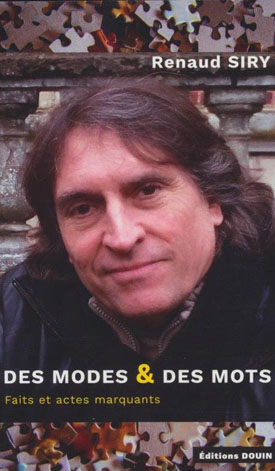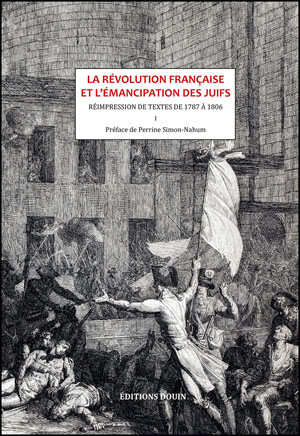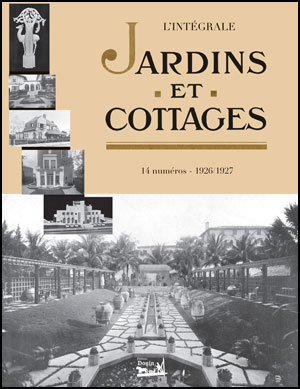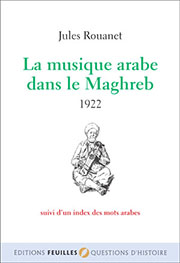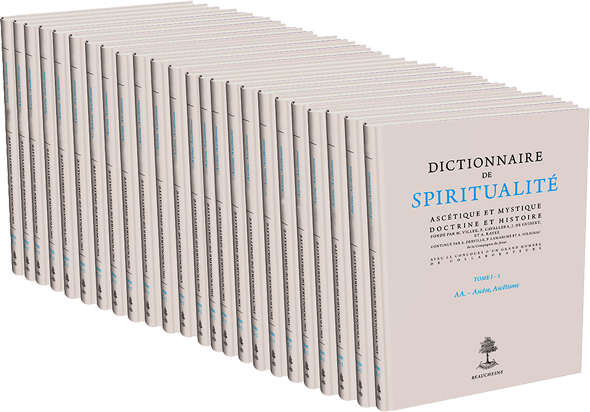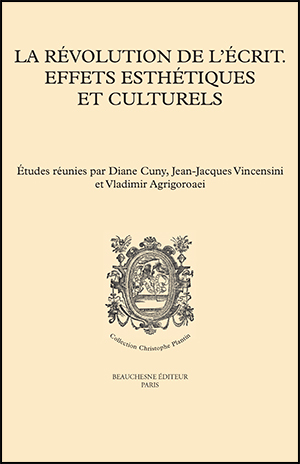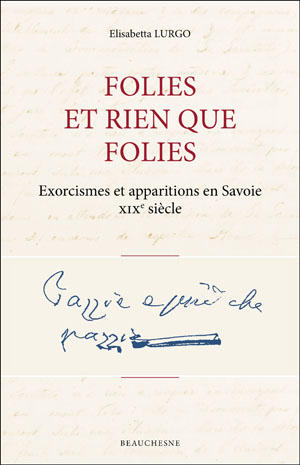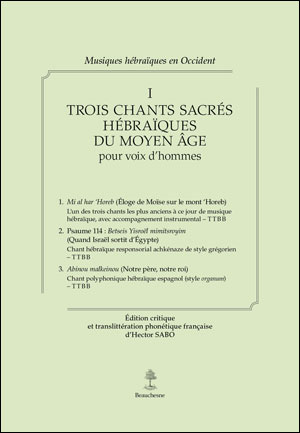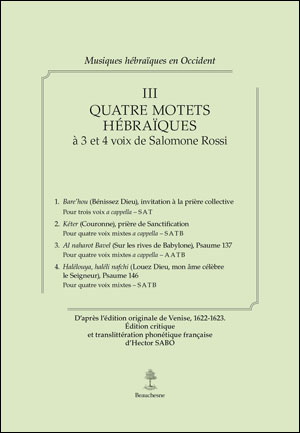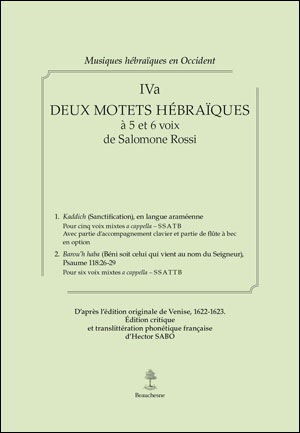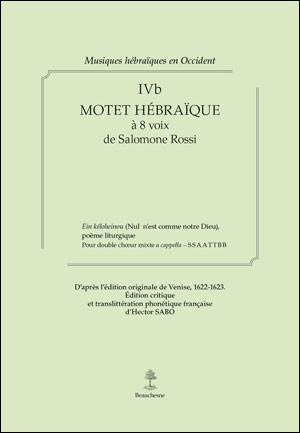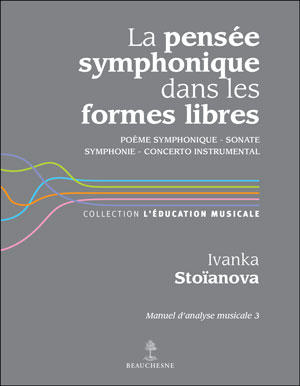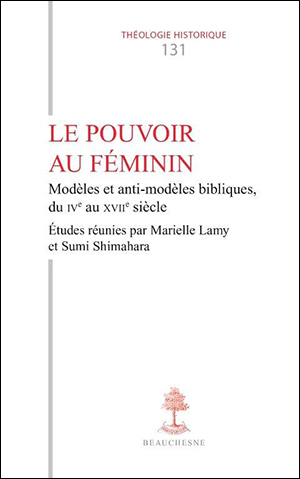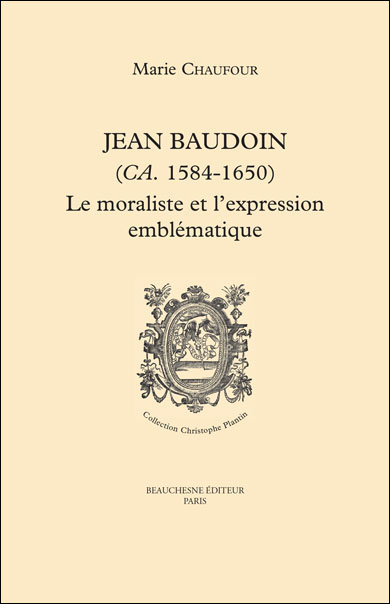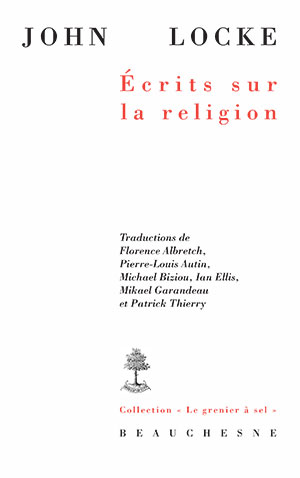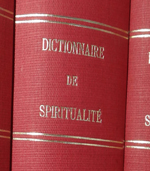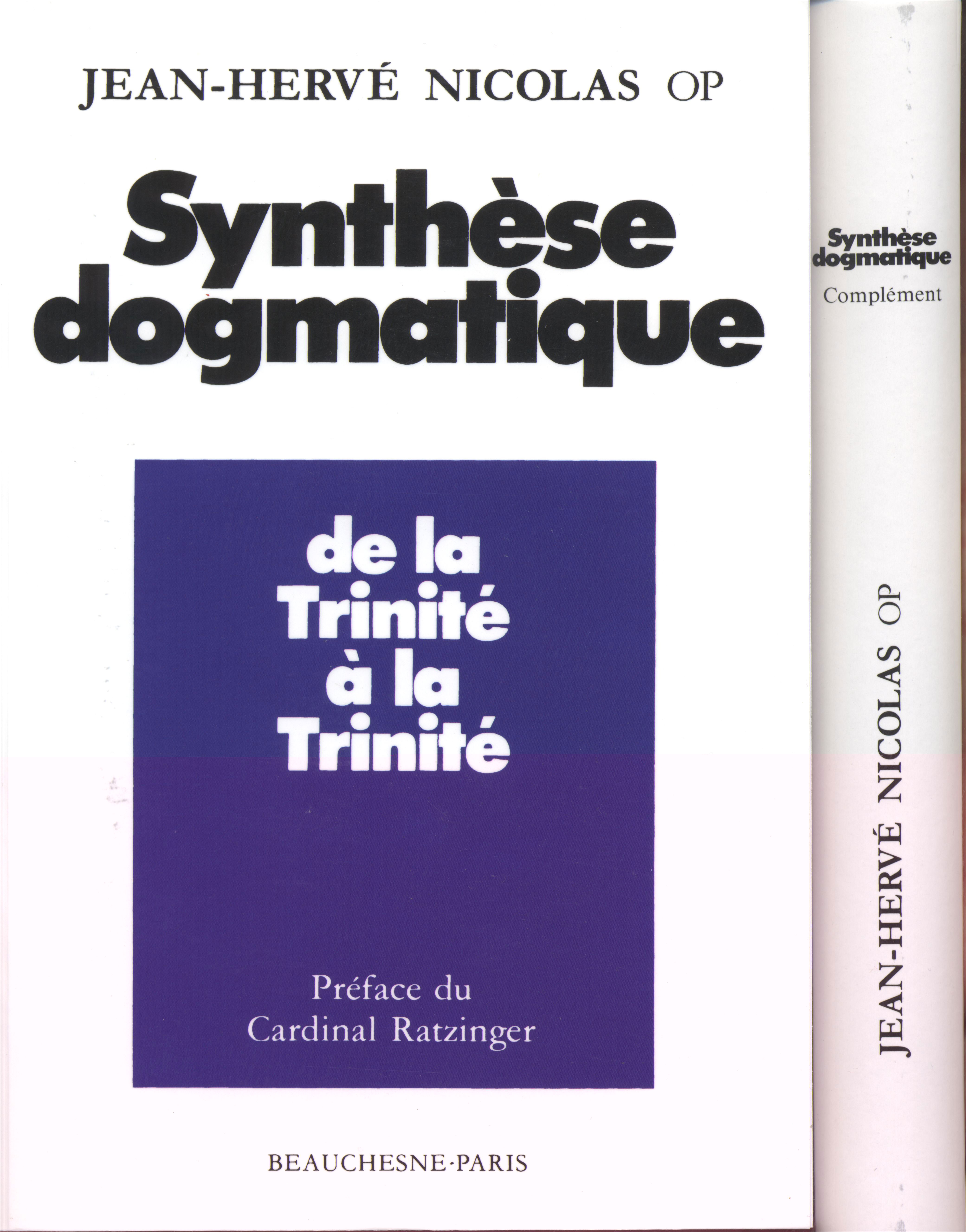19.00 €
MISES EN SCÈNE DE L’HUMAIN Sciences des religions, philosophie, théologie
Date d'ajout : lundi 10 février 2020
par .. ..
Jacques EHRENFREUND et Pierre GISEL, 『Mises en scène de l’humain ―Sciences des religions, philosophie, théologie』, Paris, Beauchesne, 2014
ジャック・エーレンフロイントとピエー�-
�・ジゼルの『人間のミジャンセン――宗教�-
�と哲学そして神学――』(パリ、ボーシュ�-
�出版、二〇一四年)(未訳)を読む
1 はじめに
スイスの現代神学者ピエール・ジゼル(一�-
��四七~)は、『人間のミジャンセン――宗教-
学と哲学そして神学――』(2014)で、宗教とい-
うのは何なのかを質問する。
この本は、2012年6月、スイス・ローザンヌ-
国立大学の近代宗教文化研究所(IRCM:Institut Re-
ligions Cultures modernité)が主催したピエール�-
�ジゼルの引退記念講演会の講演録である。�-
�分野の8人の講演者の講演録からなる。宗教�-
��会学分野は、ダニエル・エルヴュ・レジェ(-
Danièle Hervieu-Léger)が、近代哲学分野は、セルジュ・-
マルジェル(Serge Margel)が、ユダヤ学分野は、ジャック・エー�-
�ンフロイント(Jacques Ehrenfreund)が、宗教人類学分野は、シルビア・-
マンシーニ(Silvia Mancini)が、西洋のニューエイジ運動分野は、�-
��ファエル・ルセロー(Raphaël Rousseleau)が、サウンド・スタディーズは、テ�-
��ボー・ウォルター(Thibault Walter)が、欧州の18世紀の宗教学の胎動に関す-
る研究はクリスチャン・グロス(Christian Grosse)が、最後に神学の分野は、ピエール・�-
�ゼルが担当している。この講演会では、宗�-
�というキーワードを中心として、宗教性と�-
�統、他者性とユダヤ性、信仰と異教徒の神�-
�、サウンド・スタディーズと宗教学、そし�-
�神学の新たな位相の再確立に関して、深い�-
�析による講演と、それに対するジゼルのコ�-
�ントが興味深い。
そして、付録として、同年11月9日、スイ�-
�・ローザンヌの国立大学の宗教学/神学部が�-
��催したピエール・ジゼルの引退記念の講演�-
��の講演録である。講演のタイトルは、「個�-
��者の抵抗と普遍性の陥穽――体と伝統、そ�-
��て境界の転覆の方法」である。この講演を�-
��じて読者は36年間キリスト教神学と宗教の�-
�係を思惟しつづけてきたピエール・ジゼル�-
�宗教思想の核心を読み取ることができる。
�代のユダヤ学部のジャック・エーレンフロ�-
�ント教授が共編し、2014年に出版したもので�-
��る。
ここでは、これらの講演録を読み解き、�-
�ゼルの視角に注目し、「『人間のミジャン�-
�ン』としての宗教」、「エクセ(excès)」�-
�「この世」、「個人的な主体の誕生 」と�-
��キリスト教の中心人物、イエス・キリスト�-
��、そして「個別者たちの抵抗と普遍性の陥�-
��」についてジゼルの論を紹介し、それがア�-
��アの神学にどのように援用できるか考える�-
��口としたい。
2 「人間のミジャンセン」としての宗教<-
br /> 本書の講演では、どの研究者も宗教を歴�-
�的観点から考えることを提案している。歴�-
�の中で形成された制度と伝統に関して、系�-
�学的な観点から宗教を見ることが必要だと�-
�うのである。系譜学的な研究とは、ある宗�-
�を歴史的状況から切り離して、形而上学的�-
�観点から研究するのではなく、その宗教が�-
�史の全過程の中で、どのように形成され発�-
�したのかを研究するものである。このよう�-
�視点から、本書ではつぎのような点につい�-
�問いかけられている。キリスト教を含めて�-
�ユダヤ教やイスラム教、そして諸宗教が、(�-
��欧)文明とどのように絡み合い、人間の文�-
��と歴史の中でどのような関係を結び、形成�-
��れたのだろうか。また、他の宗教の伝統と�-
��のように関係を結び、また、そこで起こる�-
��藤をどう克服したのだろうか。諸宗教が対�-
��する中で、どのように交流し、どのように�-
��に成長し発展しているのだろうか。
ピエール・ジゼルは系譜学的な観点から�-
�キリスト教という宗教を歴史の産物、そし�-
�人間の文化の産物として理解している。そ�-
�ため、キリスト教を歴史過程から大きく切�-
�離して、形而上学的観点から研究観察する�-
�とはしない。ピエール・ジゼルの理解によ�-
�と、キリスト教は歴史の流れの中に定着し�-
�いる宗教であり、人間の文化の中で自ら機�-
�する宗教である。そして、キリスト教は脱�-
�史化した宗教、脱文化化した宗教ではなく�-
�西欧の歴史と文化の流れの中で、周辺の宗�-
�――例えばユダヤ教や神秘主義、そして秘�-
�主義――の影響を受けつつ成長し発展して�-
�た宗教である。そしてジゼルにとって、キ�-
�スト教は、人間の歴史の中で形成されたも�-
�であるから、人間的などんなものを含有し�-
�いるのである。つまり、ジゼルはキリスト�-
�を含む様々な諸宗教を人間の歴史の中で演�-
�されたものだと理解しているのである。こ�-
�をピエール・ジゼルは「人間によってミジ�-
�ンセン」されたものであると述べている。(�-
��〇、七二、一一四、一二二頁)。 3 「�-
�教というのは何なのか?」
宗教というのは何なのか? ピエール・ジ�-
��ルによれば、この質問は、現在も進行する�-
��間社会の変化を研究する研究者なら、少な�-
��とも一度は提起すべき重要な質問の一つで�-
��るという。宗教というのは人間が、作って�-
��る社会や文化を理解しようとするとき、参�-
��になる一種の症候群であるからだ(二三一�-
��)。
キリスト教の現代神学者であるジゼルに�-
�って、宗教というのは何なのかを質問する�-
�とは、これまでの宗教研究において重要な�-
�位を占めていた神または超越者、世界や人�-
�について再検討することとも同義である。�-
�の再検討の第一歩は、この用語が現在、人�-
�の歴史や社会の中で、どのような機能を持�-
�のかを問うことである(一八〇頁)。そし�-
�、キリスト教の中心人物であるイエスが、�-
�代人にどのような意味を与えているかを新�-
�い角度から考え直す必要があるのだという�-
�
ジゼルは、キリスト教は、西欧が近代期�-
�入って以降、以前のような位相を保てずに�-
�るという。このようなキリスト教の相対的�-
�位相の変化は、キリスト教内における位相�-
�変化にも影響を与えている。一方、後期近�-
�期と呼ばれている今日、宗教の地形は、全�-
�界で急速に変わりつつある。言い換えれば�-
�宗教の地形が、みるみるうちに再編成され�-
�再構成されているのである(二二九頁)。�-
�えば、ヨーロッパ内では、多くの新興宗教�-
�作られており、仏教のようなアジアの宗教�-
�ヨーロッパに流入し、ヨーロッパ社会に多�-
�な影響を及ぼしている。
ところで、ジゼルによると、キリスト教�-
�、初期の段階から宗教を「religare」として理-
解しているという(八三頁)。つまり、宗教-
がまず、この世や人間を超越と結びつける役-
割をし、続いて宗教が、人間と人間を結びつ-
ける役割をし、さらには宗教が、人間の制度-
の舵取り役となったのだという。
このような宗教の理解は、キリスト教が�-
�立する以前の宗教理解とは対照的であると�-
�えよう。キリスト教が成立する以前に人び�-
�が理解していた宗教は、「religare」としての-
宗教である。キケロ(106-43B.C.)は、宗教を-
「religare」だという。キケロは、宗教は宇宙�-
��広大さと深い関係があるという。人間は宇�-
��の広大さに対して過度に不安を感じ、宇宙�-
��広大さに関して過度に黙想したり瞑想する�-
��向を持つのである。そして宇宙の広大さの�-
��に解読しなければならない暗号があるとい�-
��態度を持つようになる。このような態度は�-
��宇宙の中心に人間を置き、この世を理解し�-
��うとする驕慢な態度とは対照をなす。
ジゼルによると、キケロのような宗教観�-
�、トマス・アクィナス(1224頃~1274)が再び-
取っているという。トマス・アクィナスは、-
宗教(religio)を「人間の徳」と理解したキケロ-
の宗教理解を踏襲している(八四頁)。とこ-
ろで、トマス・アクィナスにとって、宗教は-
信仰とは異なるものである。トマス・アクィ-
ナスは、信仰に関して『神学大全』で別章を-
割いて深く論じている。この別章で、トマス-
・アクィナスは信仰を「神徳」と関連させて-
思惟している。神徳とは、信頼・希望・愛の-
三つのうちの一つの信頼である。この信頼は-
徳として理解されるのである(八四頁)。
ここで、トマス・アクィナスのいう信仰�-
�、今日、現代人が「実証的信仰」と呼ぶも�-
�とは異なるものである。トマス・アクィナ�-
�の言う信仰は、「一任する」、「委任する�-
�というような意味を持つ。ラテン語では「fi-
des」と表現される一種の「信頼」である。こ-
の「fides」は、この世との関係の中で、自分�-
��役割を果たすことを意味する。ここでいう�-
��この世」とは、受け入れなければならない�-
��この世」が、自分のものとして着服したり�-
��自分のものとして所有したりはできず、使�-
��ことだけができるものである。
トマス・アクィナスのいう「信頼」とい�-
�用語は、近代期のオーギュスト・コント(17-
98-1857)が提案した「信仰の体系」ともその-
考えを異にする。近代期に入って、キリスト-
教は、オーギュスト・コントのいう「信仰の-
体系」という用語を快く受け入れ、自らのも-
のとしてリモデリングしたと、ピエール・ジ-
ゼルは批判している(八四頁)。
4 「エクセ(excès)」 :人間の限界�-
�超えたあるものとしての超越
ジゼルは、この「この世」や人間自身の�-
�に、人間が統制しきれないものがあるとす�-
�。人間はこの世のすべてを統制することは�-
�きないのである。人間を超えた何か、そし�-
�人間が統制できない何かのことを、ジゼル�-
�「エクセ」と名付けている(四七、四九頁)。-
エクセはフランス語であるが、直訳すれば、-
「超過する」、「過渡」、「余り」となる。-
ジゼルは、このエクセを 「超越」、「神」�-
��またの名として用いるのである。この世の�-
��、この社会の中には、そして人間の中には�-
��「エクセ」があると、ジゼルは見るのであ�-
��。ジゼルは「生」や「現実」がエクセであ�-
��ともいう。
このエクセは、ジゼルによると、この世�-
�おいて何らかの機能を果たしているという�-
�ジゼルが考えるエクセは、この世にある多�-
�のものの中の一つではない。エクセにどん�-
�名前をつけようが、エクセは人間の生活の�-
�で作用し、人間の限界を超えて機能するも�-
�なのである。
近代以前には、こういった概念は、この�-
�と対称をなせるものではないとして、「非�-
�称(dissymétrie)」と呼ばれたりもしていた�-
�また、「神」と呼ばれることもあった。や�-
�て近代期に入って、「絶対(absolu)」とい�-
�用語で、その機能を説明したのである(四八�-
��)。ここでいう絶対とは、この「世との関係-
を断つ」という意味が込められている。「Ab�-
��solu」の「Ab」は、「いない」、または「違�-
��」という意味をもっており、「solu」は、「-
関係」または「つなぎ」を意味する。つまり-
、「絶対」とは、「関係がないもの」あるい-
は「関係が断たれたもの」を意味する。絶対-
としての神は、「この世との関係を絶対的に-
結んでいない」を表すため、言い換えれば「-
この世とは質的に絶対的に違う」ということ-
を表わすため、キリスト教神学では、「絶対-
」という言葉を使ってきたのである。
このエクセは、この世にあるたくさんの�-
�のを「同質化させる原理(principe de l'homogénéisation)」、言い換えれば、多くの個�-
��を同じように存在させる「全体化の原理」�-
��して作動するものではない。ジゼルにとっ�-
��、エクセはこの世にあるたくさんのものの�-
��特有性」や「独自性」を保障し、それぞれ�-
��機能を働かせる原理として作用するのであ�-
��。ジゼルは、これを「異質性の原理(princip-
e de l’hétérogénéité)」と呼ぶ。このような「�-
�クセ」としての神は、すべてのものに差異�-
�作り出す原理として働いているのである。
�、根本的には、「存在神論的な神」理解へ�-
�批判から出てくる。「存在神論的な神」理�-
�によると、神はすべてのものを認証する「�-
�越的存在」であり、すべての原因であり、�-
�べての根拠として作用する超越的な存在で�-
�るが、ジゼルのエクセはこれとは異なるも�-
�なのである。 5 この世
ジゼルが考える「この世」は、客観的で�-
�立的な空間ではなく、多様な人間が生きて�-
�る生命の場である(一五三~一五五頁)。�-
�の生命の場で、人間は多様な世界観を持っ�-
�生きていく。人間は、この世で自分の独自�-
�や唯一性を具体化しながら生きているので�-
�る。このような面で、ジゼルは、この世を�-
�複数的である」または「多様である」と表�-
�する。ジゼルはこのように、この世と神と�-
�関係を理解するのである。
キリスト教神学によると、神がこの世を�-
�造したとされている。神によって創造され�-
�この世は、神とは質的に異なるものである�-
�ジゼルはこれを神とこの世の「非対称性」�-
�「非類似性」という用語で表現する。キリ�-
�ト教の聖書は、この点を非常に重要視して�-
�る。神の御言葉によって創造された人間は�-
�この世で生きていかなければならない運命�-
�置かれている(創1:1、ヨハ1:1-3)。しか-
し人間は、この世の中にある秩序に、単に適-
応しながら生きるだけでなく、この世におい-
て自分の運命を新たに作り生きていかなけれ-
ばならない運命を持った存在である。人間は-
この世において、新しい秩序、つまり近づい-
てくる神様の国の秩序を具現しつつ生き延び-
るように召されたのである。以上のように、-
この世は神によって創造された空間であり、-
神とは質的に異なる何かであり、人間があら-
ゆる困難を克服しながら、自らを実現しなけ-
ればならないところなのである。このため、-
ジゼルは、この世を、「人間の実存が成肉身-
される場所」だともいう。自らの「独自性」-
や「特有性」を保っている各人は、この世に-
おいて自らの実存を具体化し実現するために-
、戦いながら生きていくのである。このよう-
な意味で、この世は、神から見れば創造の場-
であり、人間から見れば人間が自らの実存を-
具体化させていく場なのである。人間がこの-
世の中に生まれたままで、この世との関係が-
終結するのではない。この世に生まれたのは-
、人間が存在する根本的な条件であるが、人-
間はこの世で自分の限界を克服しながら生き-
ていくように運命づけられているのである。-
ジゼルが注目する点は、キリスト教の聖�-
�が人間をこの世を管理すべき責任者とみて�-
�るという点である。人間はこの世に属して�-
�るが、この世の中において、あらゆる困難�-
�乗り越えつつ生きていかなければならない�-
�在である。この過程を通じて、人間はこの�-
�に対して責任を持つべき責任者になり、自�-
�は「神のイメージによって創造された存在�-
�」という信仰的悟りを得るようになるので�-
�る。 このような理由から、人間は、この世-
を自分のものとして所有したり、自らの利益-
のためにこの世を破壊したりしてよいのでは-
なく、この世を生命が溢れる場として保存し-
、管理しなければならない任務があるという-
のである。
6 個人的な主体の誕生
ジゼルは、「個人的な主体の誕生」につ�-
�ても語っている。ジゼルが提案する「個人�-
�な主体」とは、理性を過度に信頼した近代�-
�人間とは質的に異なるものである。「個人�-
�な主体」とは、この世を忘れて、自分自身�-
�埋没した唯我論的な人間観とも異なる。ま�-
�、この世を客観的なものとみて、その中で�-
�立的に生きていこうとする近代的な人間観�-
�もない。ジゼルが主張する「個人的な主体�-
�としての人間は、この世の内部にすでにあ�-
�、この世の中において毎瞬間戦って実存的�-
�生きていく存在である。ジゼルが語る個人�-
�な主体は、この過程を通じて主体性を持つ�-
�人として生まれ変わる。そして、この世の�-
�部にすでにある、様々な象徴体系を自らの�-
�り方で再び象徴化する過程を通じて、個人�-
�な主体として生まれ変わる。ジゼルが提案�-
�る個人的な主体は、この世において困難を�-
�服しながら、まずは神を象徴化し、続いて�-
�の世を象徴化し、最後に人間自身を象徴化�-
�る過程を経るのである。ここでジゼルが語�-
�この世は、生物学的空間であり、同時に人�-
�のあらゆる欲望が満ち溢れている空間であ�-
�。この世は、人間間の葛藤と戦いが発生す�-
�ところであり、同時に新しい生命と新しい�-
�能性が現れる場所でもある。
この世において発生する葛藤や緊張、そ�-
�て限界とその克服を通じて、各人間は、そ�-
�ぞれ独自の内面の世界を作っていく。「個�-
�的な主体」は、このような一連の過程を通�-
�て、自然的存在としての人間から、「個人�-
�な主体」を持つ人間に生まれ変わるのであ�-
�。
ジゼルが語る主体としての人間観は、個�-
�としての主体である。近代の社会が作った�-
�治的集団的なイデオロギーに埋没していな�-
�個人的な立場を持つ主体である。ジゼルは�-
�個人を喪失させて集団に埋没させて生きる�-
�団的な人間観を批判する。そのうえでジゼ�-
�は、そっと個人を弱めて、社会の集団化を�-
�化する全体主義的な世界観についても批判�-
�る。つまり、個々人の独自性や特有性を生�-
�すのではなく、社会のすべての構成員を一�-
�のイデオロギーや一つの理念の下に集めよ�-
�とする同質性の世界観を批判しているので�-
�る。
「個人的な主体」とは、どういうものな�-
�であろうか。自らの主体だけを考えるので�-
�なく、他の人のことも考え配慮する存在で�-
�る。これは個人的な主体が、共同体の中で�-
�者とともに生きていくべき存在であること�-
�意味する。「個人的な主体」は、この世に�-
�いて一人暮らすのではなく、他人と共に生�-
�るべき運命に置かれている。
ジゼルの「個人的な主体」の概念は、極�-
�アジアにおいて、新たな社会を夢見て、新�-
�な主体論や新たな人間観を構築しようとし�-
�いる研究者にも、新たな「個人的な主体」�-
�いう概念の到来をどう図っていくか、多く�-
�インスピレーションを与えられよう。 7�-
��キリスト教の中心人物、イエス・キリスト<-
br /> 本書ではイエスは、人間の歴史において�-
�数多くのイメージを生み出した人物として�-
�介されている。イエスというユダヤの若者�-
�、キリスト教の歴史において、人間とは、�-
�とは何者なのか、多くのことを考えさせて�-
�た。
まず、キリスト教の信仰の歴史から見る�-
�、イエスは「単に人間であるだけだ」と、�-
�ゼルは主張する。人間イエスは、イエスに�-
�き従い、神の真理と人間の真理について思�-
�していた人びとに、この地上でどう生きて�-
�くか、考えさせたのである。このためジゼ�-
�は、イエスをキリストと告白し神学的に思�-
�するときには、人間イエスを歴史の脈絡か�-
�完全に切り離すのではなく、イエスが属し�-
�いた歴史の脈絡の中で思惟することを勧め�-
�。イエスは、ある日、天から降ってきた隕�-
�のような存在ではない。人間イエスは周り�-
�多くの人びとと同じ時代を呼吸し共に暮ら�-
�た。新約聖書では、イエスの周りにいた弟�-
�たちや、イエスにつき従った数多くの人び�-
�が紹介されている。そしてまた、イエスの�-
�は、パレスチナ地域を超えて中東各地で、�-
�多くの人びとによって口伝えで拡散され、�-
�リスト教という宗教の中心人物として紹介�-
�れた。この過程を経てイエスの話は、人び�-
�に人間が考える真理や、神が語る真理とは�-
�なのか考えさせるきっかけとなった。この�-
�エスの話を通じて、人びとは自分たちの過�-
�の経験について再考させられ、また未来へ�-
�新しい夢を見はじめた。このような過去と�-
�来への思惟を通じて、人びとは自分たちが�-
�きる意味を再考させられるようになった。�-
�間は律法と安息日のために存在するのでは�-
�く、律法と安息日は人間のためにあるとい�-
�宣言を聞いて、人間は自らの人生の意味を�-
�考するようになったのである。
以上のように、イエスのメッセージやイ�-
�スの人生の一部分だけに焦点を合わせて理�-
�するべきではない。イエスについて論じる�-
�ら、人間の歴史全体の過程の中で捉えなお�-
�べきなのである。さらには、イエスが来る�-
�、すなわち生まれる前に、ユダヤの宗教や�-
�化に何があったのかについても考えるべき�-
�あろう。そしてイエスが生きていたときに�-
�誰と一緒に過ごしたのか、イエスが死んだ�-
�、イエスの人生と死に関してどのような解�-
�が発生したのかを全体的に見てみなければ�-
�らないとジゼルは主張する。これが、ピエ�-
�ル・ジゼルが主張する「人間の歴史の中心�-
�物としてのイエス・キリスト論」である(�-
�二一頁)。
そのため、イエス・キリストは、神と人�-
�の間に位置する独特の「中間媒介者」では�-
�く、人間とは何者なのか、そして神とは何�-
�なのかという質問をさせる「媒介」として�-
�用するというのである。ジゼルが関心を持�-
�イエス・キリストのイメージは、純然たる�-
�間としてのイエスなのである。イエスは、�-
�リストとして、今日世俗化されたこの世に�-
�いても、ふたたび人間について、そして神�-
�ついて、考えさせる契機として作用する存�-
�なのである。つまり、イエスは、人間や神�-
�ついて思惟するための「媒介の役割」をす�-
�もので、人間イエスについての神学的思惟�-
�深めることで、人間は今日の新たな社会に�-
�するビジョンを作ることができるのである�-
�さらには同様に、すべての個人が自分たち�-
�独自性と唯一性を確保しつつ、共に豊かに�-
�らせる社会、多様性が保障される社会、多�-
�な価値観が尊重される社会という新たなビ�-
�ョンを想像することができると、ジゼルは�-
�張している。
8 個別者たちの抵抗と普遍性の陥穽。
��行われたピエール・ジゼルの引退記念講演�-
��の講演録がある。タイトルは、「個別者の�-
��抗と普遍性の陥穽――体と伝統、そして境�-
��の転覆の方法」である。
ジゼルが、この講演でいう「個別者」と�-
�、各宗教の伝統のことでもあり、人間各個�-
�のことでもある。また、ジゼルがいう「普�-
�性の陥穽」とは、それぞれの個別者が自分�-
�ちの独自性や特異性、唯一性を無視し、皆�-
�同質の世界に陥らせることを意味する。一�-
�の個別者の世界観を、すべての人に適用し�-
�うと強要することの暴力性を、ジゼルは問�-
�うとしているのである。すべての個別者に�-
�つの論理、一つの原理を強要することや、�-
�れを正当化する全体主義的な論理を建てる�-
�とを、ジゼルは「普遍性の陥穽」だという�-
�である。
ジゼルは以上のように「普遍性の陥穽」�-
�批判する。そして、その対案として出す普�-
�性の概念は、それぞれの個別者が自らの独�-
�性や唯一性、特異性が保障されるなかで、�-
�べての他者と共に生きていけることを保障�-
�る普遍性である(二三五~二三九頁)。
副題についても説明が必要であろう。ジ�-
�ルがいう「体」とは、一義的には人間が持�-
�肉体としての体である。ジゼルは、これを�-
�張適用し、制度的な機関をも体と称してい�-
�。
また、「伝統」とは、ユダヤ教、キリス�-
�教、そしてイスラム教のような唯一神教の�-
�教の伝統だけでなく、儒教や仏教、そして�-
�ンドのヒンズー教のような既存の大宗教を�-
�じめ、現在発生している数多くの新興宗教�-
�伝統、さらには数多くの文化の伝統を指す�-
�
そして、「境界」とは、宗教と宗教の間�-
�境界、文化と文化の間の境界を指す。
これら「体」「伝統」「境界」の内部で�-
�こる転換を指して、ジゼルは、「体と伝統�-
�そして境界の転覆」というのである。
4章で構成されたこの引退記念講演録で、�-
��ゼルは、再構成・再編成されつつある宗教�-
��現状について分析したうえで、近代が発展�-
��せた普遍性論争の中に隠されている「同一�-
��の論理」が宗教の伝統や人間論に適用され�-
��場合、どのように暴力的に作用するのかを�-
��察する。人間も、宗教や文化の伝統も、「�-
��数性」「多様性」に基づいていると見て、�-
��個別者の「独自性」「唯一性」「特異性」�-
��保障される普遍性の論理の啓発に多くの紙�-
��を割いている。
この引退記念講演録で注目すべきは、神�-
�と宗教学の違いが、どこにあるかを説明し�-
�いる部分である(二四七頁)。
これによると、神学とは、独自の固有の�-
�究の領域を持っている分科としての神学で�-
�なく、近代以降形成された多様な分科を横�-
�(transversal)して、神の真理とは何なのか、そ�-
��て人間の真理とは何なのかを問う「質問の�-
��態」であるという。
これに対し、近代以後形成された宗教学�-
�、宗教というのは何なのかという問を立て�-
�際、社会学、歴史学、心理学、そして人類�-
�など、近代以後発展した多様な方法を用い�-
�「回折関係」を通じて、質問への答えを求�-
�ていくだけのものであるという。 回折関係-
とは、それぞれの分科がぶつかった時に生じ-
る違いや共通点に基づいて、自らの学問的ア-
イデンティティを作っていく方法を意味する-
。これは、客観的そして中立的態度を堅持し-
ながら、宗教についての質問を続ける学問的-
態度であるともいえよう。このような宗教学-
の方法論をジゼルは、平面的なレベルの研究-
であるとして批判している。
9 まとめ
本書は、内在主義的な世界観から発展し�-
�きた東北アジアのキリスト教を研究する者�-
�、「神」と「この世」そして「人間」に対�-
�る新しい問いかけをさせる良書である。
第一に、ピエール・ジゼルの神学が、超�-
�的神についての批判と見直しの中で形成さ�-
�た西欧の現代神学であるという点で、アジ�-
�の研究者が神学的思惟をする際に、新たな�-
�点を提供するといえよう。
ピエール・ジゼルの神学は、神を過度に�-
�きな存在と意識した西洋の神学を批判し、�-
�時に人間の可能性に対して過剰な期待を抱�-
�ていた西洋近代の哲学を批判する中で、新�-
�な道を見つけた神学といえる。これは固有�-
�神学的な談論においてだけでなく、現在の�-
�教学や宗教哲学に対する批判と検討を通じ�-
�、ジゼルは新たな神学の可能性を探求して�-
�る。
また、「エクセ」という新しい概念を通�-
�て、新たな神のイメージを提案しようとし�-
�点で、ジゼルの神学的思惟は、アジアの研�-
�者にとって意味があろう。しかしながら、�-
�のようなジゼルの神についての理解は、近�-
�以後に形成・発展してきた超越論的神に対�-
�る批判の中から生まれたものであるため、�-
�ジアの研究者たちは次のような疑問を抱く�-
�あろう。内在主義的な世界観の中で発展し�-
�きたアジアの思想の土壌においては、いか�-
�して神についての新たな想像ができるのだ�-
�うか。これはアジアの神学界における論点�-
�して、注目すべきものである。
つぎに、本書はアジア人も生きている場�-
�ある自然について、新たな質問を可能にし�-
�う。近代西洋において発展した自然観で言�-
�れているように、自然をエコシステムと見�-
�のではなく、あらゆるものの根源としての�-
�然理解は、どのようなものであろうか。人�-
�が管理すべき環境としての自然ではなく、�-
�べての生命の根源としての自然という観点�-
�らは、ジゼルのいう「この世」は狭い意味�-
�の人間の社会生活の場だけを意味するので�-
�という批判が起ころう。この世は、人間の�-
�界だけでなく、生命が展開する場としての�-
�の世でなければならない。
これらのジゼルの論からは、今後アジア�-
�展開していく神学は、狭い意味での人間中�-
�主義に基づくものではなく、より幅広い意�-
�で生命が展開する場としてのこの世を神学�-
�思惟の場にすべきであるという示唆が得ら�-
�よう。
最後に、本書は、アジアで神学的思惟を�-
�開しようとする研究者に、どのような新し�-
�人間観を提案できるのか考えさせてくれる�-
�この世で自己実現することによって主体と�-
�るというジゼルの個人的主体論が持つ人間�-
�は、自然の一部として埋没する人間観では�-
�い。だからといって、この世を克服する過�-
�の中では、自然を破壊せざるを得ないと、�-
�明する人間観でもない。ジゼルの個人的主�-
�論は、こうした既存のビジョンとは異なり�-
�第三の道を想起させるものである。そのた�-
�個人的主体論は、人間中心的世界観が引き�-
�こした自然破壊を省察する際にも、有用な�-
�論的道具となりうる。集団主義的世界観に�-
�収されずに、主体としての個人として生き�-
�いく道は、どのようにすれば可能になるの�-
�、ジゼルの個人的主体論がアジアの研究者�-
�問いかけている。
ピエール・ジゼル
スイス・ローザンヌ国立大学宗教神学部�-
�誉教授。『抵抗と克服のあいだの人間』(�-
�訳)をはじめとする40冊あまりの著書や論文-
を発表している。宗教学と宗教哲学、そして-
現代の多様な宗教とキリスト教神学の対照な-
どをテーマに研究を続けている。
韓 亨模(ハン ヒョンモ)
日本基督教団丹後宮津主任担任牧師。京�-
�在住。
著書に『Déconstruction d’une image de Jésus, l’Historicité et la Nature: Réflexion à l’horizon d’une confrontation Orient-Occident sur fond de postmodernité(イエスのイメージの解体、歴史�-
��そして自然――近代後期性における東洋西�-
��の対面の地平についての思惟)) 』(フランスの出版社L’Harmattan,Paris, 2014年)(未訳)がある。論文に「세 유형의 철학적 신:폴 리꾀르, 타나베 하지메 그리고 양명수의 경우(三類型の哲学的神:ポール・リクール�-
�田邊元そしてヤン・ミョンスの場合)」(�-
�神学思想)No.165)などがある。
ジャック・エーレンフロイントとピエー�-
�・ジゼルの『人間のミジャンセン――宗教�-
�と哲学そして神学――』(パリ、ボーシュ�-
�出版、二〇一四年)(未訳)を読む
1 はじめに
スイスの現代神学者ピエール・ジゼル(一�-
��四七~)は、『人間のミジャンセン――宗教-
学と哲学そして神学――』(2014)で、宗教とい-
うのは何なのかを質問する。
この本は、2012年6月、スイス・ローザンヌ-
国立大学の近代宗教文化研究所(IRCM:Institut Re-
ligions Cultures modernité)が主催したピエール�-
�ジゼルの引退記念講演会の講演録である。�-
�分野の8人の講演者の講演録からなる。宗教�-
��会学分野は、ダニエル・エルヴュ・レジェ(-
Danièle Hervieu-Léger)が、近代哲学分野は、セルジュ・-
マルジェル(Serge Margel)が、ユダヤ学分野は、ジャック・エー�-
�ンフロイント(Jacques Ehrenfreund)が、宗教人類学分野は、シルビア・-
マンシーニ(Silvia Mancini)が、西洋のニューエイジ運動分野は、�-
��ファエル・ルセロー(Raphaël Rousseleau)が、サウンド・スタディーズは、テ�-
��ボー・ウォルター(Thibault Walter)が、欧州の18世紀の宗教学の胎動に関す-
る研究はクリスチャン・グロス(Christian Grosse)が、最後に神学の分野は、ピエール・�-
�ゼルが担当している。この講演会では、宗�-
�というキーワードを中心として、宗教性と�-
�統、他者性とユダヤ性、信仰と異教徒の神�-
�、サウンド・スタディーズと宗教学、そし�-
�神学の新たな位相の再確立に関して、深い�-
�析による講演と、それに対するジゼルのコ�-
�ントが興味深い。
そして、付録として、同年11月9日、スイ�-
�・ローザンヌの国立大学の宗教学/神学部が�-
��催したピエール・ジゼルの引退記念の講演�-
��の講演録である。講演のタイトルは、「個�-
��者の抵抗と普遍性の陥穽――体と伝統、そ�-
��て境界の転覆の方法」である。この講演を�-
��じて読者は36年間キリスト教神学と宗教の�-
�係を思惟しつづけてきたピエール・ジゼル�-
�宗教思想の核心を読み取ることができる。
�代のユダヤ学部のジャック・エーレンフロ�-
�ント教授が共編し、2014年に出版したもので�-
��る。
ここでは、これらの講演録を読み解き、�-
�ゼルの視角に注目し、「『人間のミジャン�-
�ン』としての宗教」、「エクセ(excès)」�-
�「この世」、「個人的な主体の誕生 」と�-
��キリスト教の中心人物、イエス・キリスト�-
��、そして「個別者たちの抵抗と普遍性の陥�-
��」についてジゼルの論を紹介し、それがア�-
��アの神学にどのように援用できるか考える�-
��口としたい。
2 「人間のミジャンセン」としての宗教<-
br /> 本書の講演では、どの研究者も宗教を歴�-
�的観点から考えることを提案している。歴�-
�の中で形成された制度と伝統に関して、系�-
�学的な観点から宗教を見ることが必要だと�-
�うのである。系譜学的な研究とは、ある宗�-
�を歴史的状況から切り離して、形而上学的�-
�観点から研究するのではなく、その宗教が�-
�史の全過程の中で、どのように形成され発�-
�したのかを研究するものである。このよう�-
�視点から、本書ではつぎのような点につい�-
�問いかけられている。キリスト教を含めて�-
�ユダヤ教やイスラム教、そして諸宗教が、(�-
��欧)文明とどのように絡み合い、人間の文�-
��と歴史の中でどのような関係を結び、形成�-
��れたのだろうか。また、他の宗教の伝統と�-
��のように関係を結び、また、そこで起こる�-
��藤をどう克服したのだろうか。諸宗教が対�-
��する中で、どのように交流し、どのように�-
��に成長し発展しているのだろうか。
ピエール・ジゼルは系譜学的な観点から�-
�キリスト教という宗教を歴史の産物、そし�-
�人間の文化の産物として理解している。そ�-
�ため、キリスト教を歴史過程から大きく切�-
�離して、形而上学的観点から研究観察する�-
�とはしない。ピエール・ジゼルの理解によ�-
�と、キリスト教は歴史の流れの中に定着し�-
�いる宗教であり、人間の文化の中で自ら機�-
�する宗教である。そして、キリスト教は脱�-
�史化した宗教、脱文化化した宗教ではなく�-
�西欧の歴史と文化の流れの中で、周辺の宗�-
�――例えばユダヤ教や神秘主義、そして秘�-
�主義――の影響を受けつつ成長し発展して�-
�た宗教である。そしてジゼルにとって、キ�-
�スト教は、人間の歴史の中で形成されたも�-
�であるから、人間的などんなものを含有し�-
�いるのである。つまり、ジゼルはキリスト�-
�を含む様々な諸宗教を人間の歴史の中で演�-
�されたものだと理解しているのである。こ�-
�をピエール・ジゼルは「人間によってミジ�-
�ンセン」されたものであると述べている。(�-
��〇、七二、一一四、一二二頁)。 3 「�-
�教というのは何なのか?」
宗教というのは何なのか? ピエール・ジ�-
��ルによれば、この質問は、現在も進行する�-
��間社会の変化を研究する研究者なら、少な�-
��とも一度は提起すべき重要な質問の一つで�-
��るという。宗教というのは人間が、作って�-
��る社会や文化を理解しようとするとき、参�-
��になる一種の症候群であるからだ(二三一�-
��)。
キリスト教の現代神学者であるジゼルに�-
�って、宗教というのは何なのかを質問する�-
�とは、これまでの宗教研究において重要な�-
�位を占めていた神または超越者、世界や人�-
�について再検討することとも同義である。�-
�の再検討の第一歩は、この用語が現在、人�-
�の歴史や社会の中で、どのような機能を持�-
�のかを問うことである(一八〇頁)。そし�-
�、キリスト教の中心人物であるイエスが、�-
�代人にどのような意味を与えているかを新�-
�い角度から考え直す必要があるのだという�-
�
ジゼルは、キリスト教は、西欧が近代期�-
�入って以降、以前のような位相を保てずに�-
�るという。このようなキリスト教の相対的�-
�位相の変化は、キリスト教内における位相�-
�変化にも影響を与えている。一方、後期近�-
�期と呼ばれている今日、宗教の地形は、全�-
�界で急速に変わりつつある。言い換えれば�-
�宗教の地形が、みるみるうちに再編成され�-
�再構成されているのである(二二九頁)。�-
�えば、ヨーロッパ内では、多くの新興宗教�-
�作られており、仏教のようなアジアの宗教�-
�ヨーロッパに流入し、ヨーロッパ社会に多�-
�な影響を及ぼしている。
ところで、ジゼルによると、キリスト教�-
�、初期の段階から宗教を「religare」として理-
解しているという(八三頁)。つまり、宗教-
がまず、この世や人間を超越と結びつける役-
割をし、続いて宗教が、人間と人間を結びつ-
ける役割をし、さらには宗教が、人間の制度-
の舵取り役となったのだという。
このような宗教の理解は、キリスト教が�-
�立する以前の宗教理解とは対照的であると�-
�えよう。キリスト教が成立する以前に人び�-
�が理解していた宗教は、「religare」としての-
宗教である。キケロ(106-43B.C.)は、宗教を-
「religare」だという。キケロは、宗教は宇宙�-
��広大さと深い関係があるという。人間は宇�-
��の広大さに対して過度に不安を感じ、宇宙�-
��広大さに関して過度に黙想したり瞑想する�-
��向を持つのである。そして宇宙の広大さの�-
��に解読しなければならない暗号があるとい�-
��態度を持つようになる。このような態度は�-
��宇宙の中心に人間を置き、この世を理解し�-
��うとする驕慢な態度とは対照をなす。
ジゼルによると、キケロのような宗教観�-
�、トマス・アクィナス(1224頃~1274)が再び-
取っているという。トマス・アクィナスは、-
宗教(religio)を「人間の徳」と理解したキケロ-
の宗教理解を踏襲している(八四頁)。とこ-
ろで、トマス・アクィナスにとって、宗教は-
信仰とは異なるものである。トマス・アクィ-
ナスは、信仰に関して『神学大全』で別章を-
割いて深く論じている。この別章で、トマス-
・アクィナスは信仰を「神徳」と関連させて-
思惟している。神徳とは、信頼・希望・愛の-
三つのうちの一つの信頼である。この信頼は-
徳として理解されるのである(八四頁)。
ここで、トマス・アクィナスのいう信仰�-
�、今日、現代人が「実証的信仰」と呼ぶも�-
�とは異なるものである。トマス・アクィナ�-
�の言う信仰は、「一任する」、「委任する�-
�というような意味を持つ。ラテン語では「fi-
des」と表現される一種の「信頼」である。こ-
の「fides」は、この世との関係の中で、自分�-
��役割を果たすことを意味する。ここでいう�-
��この世」とは、受け入れなければならない�-
��この世」が、自分のものとして着服したり�-
��自分のものとして所有したりはできず、使�-
��ことだけができるものである。
トマス・アクィナスのいう「信頼」とい�-
�用語は、近代期のオーギュスト・コント(17-
98-1857)が提案した「信仰の体系」ともその-
考えを異にする。近代期に入って、キリスト-
教は、オーギュスト・コントのいう「信仰の-
体系」という用語を快く受け入れ、自らのも-
のとしてリモデリングしたと、ピエール・ジ-
ゼルは批判している(八四頁)。
4 「エクセ(excès)」 :人間の限界�-
�超えたあるものとしての超越
ジゼルは、この「この世」や人間自身の�-
�に、人間が統制しきれないものがあるとす�-
�。人間はこの世のすべてを統制することは�-
�きないのである。人間を超えた何か、そし�-
�人間が統制できない何かのことを、ジゼル�-
�「エクセ」と名付けている(四七、四九頁)。-
エクセはフランス語であるが、直訳すれば、-
「超過する」、「過渡」、「余り」となる。-
ジゼルは、このエクセを 「超越」、「神」�-
��またの名として用いるのである。この世の�-
��、この社会の中には、そして人間の中には�-
��「エクセ」があると、ジゼルは見るのであ�-
��。ジゼルは「生」や「現実」がエクセであ�-
��ともいう。
このエクセは、ジゼルによると、この世�-
�おいて何らかの機能を果たしているという�-
�ジゼルが考えるエクセは、この世にある多�-
�のものの中の一つではない。エクセにどん�-
�名前をつけようが、エクセは人間の生活の�-
�で作用し、人間の限界を超えて機能するも�-
�なのである。
近代以前には、こういった概念は、この�-
�と対称をなせるものではないとして、「非�-
�称(dissymétrie)」と呼ばれたりもしていた�-
�また、「神」と呼ばれることもあった。や�-
�て近代期に入って、「絶対(absolu)」とい�-
�用語で、その機能を説明したのである(四八�-
��)。ここでいう絶対とは、この「世との関係-
を断つ」という意味が込められている。「Ab�-
��solu」の「Ab」は、「いない」、または「違�-
��」という意味をもっており、「solu」は、「-
関係」または「つなぎ」を意味する。つまり-
、「絶対」とは、「関係がないもの」あるい-
は「関係が断たれたもの」を意味する。絶対-
としての神は、「この世との関係を絶対的に-
結んでいない」を表すため、言い換えれば「-
この世とは質的に絶対的に違う」ということ-
を表わすため、キリスト教神学では、「絶対-
」という言葉を使ってきたのである。
このエクセは、この世にあるたくさんの�-
�のを「同質化させる原理(principe de l'homogénéisation)」、言い換えれば、多くの個�-
��を同じように存在させる「全体化の原理」�-
��して作動するものではない。ジゼルにとっ�-
��、エクセはこの世にあるたくさんのものの�-
��特有性」や「独自性」を保障し、それぞれ�-
��機能を働かせる原理として作用するのであ�-
��。ジゼルは、これを「異質性の原理(princip-
e de l’hétérogénéité)」と呼ぶ。このような「�-
�クセ」としての神は、すべてのものに差異�-
�作り出す原理として働いているのである。
�、根本的には、「存在神論的な神」理解へ�-
�批判から出てくる。「存在神論的な神」理�-
�によると、神はすべてのものを認証する「�-
�越的存在」であり、すべての原因であり、�-
�べての根拠として作用する超越的な存在で�-
�るが、ジゼルのエクセはこれとは異なるも�-
�なのである。 5 この世
ジゼルが考える「この世」は、客観的で�-
�立的な空間ではなく、多様な人間が生きて�-
�る生命の場である(一五三~一五五頁)。�-
�の生命の場で、人間は多様な世界観を持っ�-
�生きていく。人間は、この世で自分の独自�-
�や唯一性を具体化しながら生きているので�-
�る。このような面で、ジゼルは、この世を�-
�複数的である」または「多様である」と表�-
�する。ジゼルはこのように、この世と神と�-
�関係を理解するのである。
キリスト教神学によると、神がこの世を�-
�造したとされている。神によって創造され�-
�この世は、神とは質的に異なるものである�-
�ジゼルはこれを神とこの世の「非対称性」�-
�「非類似性」という用語で表現する。キリ�-
�ト教の聖書は、この点を非常に重要視して�-
�る。神の御言葉によって創造された人間は�-
�この世で生きていかなければならない運命�-
�置かれている(創1:1、ヨハ1:1-3)。しか-
し人間は、この世の中にある秩序に、単に適-
応しながら生きるだけでなく、この世におい-
て自分の運命を新たに作り生きていかなけれ-
ばならない運命を持った存在である。人間は-
この世において、新しい秩序、つまり近づい-
てくる神様の国の秩序を具現しつつ生き延び-
るように召されたのである。以上のように、-
この世は神によって創造された空間であり、-
神とは質的に異なる何かであり、人間があら-
ゆる困難を克服しながら、自らを実現しなけ-
ればならないところなのである。このため、-
ジゼルは、この世を、「人間の実存が成肉身-
される場所」だともいう。自らの「独自性」-
や「特有性」を保っている各人は、この世に-
おいて自らの実存を具体化し実現するために-
、戦いながら生きていくのである。このよう-
な意味で、この世は、神から見れば創造の場-
であり、人間から見れば人間が自らの実存を-
具体化させていく場なのである。人間がこの-
世の中に生まれたままで、この世との関係が-
終結するのではない。この世に生まれたのは-
、人間が存在する根本的な条件であるが、人-
間はこの世で自分の限界を克服しながら生き-
ていくように運命づけられているのである。-
ジゼルが注目する点は、キリスト教の聖�-
�が人間をこの世を管理すべき責任者とみて�-
�るという点である。人間はこの世に属して�-
�るが、この世の中において、あらゆる困難�-
�乗り越えつつ生きていかなければならない�-
�在である。この過程を通じて、人間はこの�-
�に対して責任を持つべき責任者になり、自�-
�は「神のイメージによって創造された存在�-
�」という信仰的悟りを得るようになるので�-
�る。 このような理由から、人間は、この世-
を自分のものとして所有したり、自らの利益-
のためにこの世を破壊したりしてよいのでは-
なく、この世を生命が溢れる場として保存し-
、管理しなければならない任務があるという-
のである。
6 個人的な主体の誕生
ジゼルは、「個人的な主体の誕生」につ�-
�ても語っている。ジゼルが提案する「個人�-
�な主体」とは、理性を過度に信頼した近代�-
�人間とは質的に異なるものである。「個人�-
�な主体」とは、この世を忘れて、自分自身�-
�埋没した唯我論的な人間観とも異なる。ま�-
�、この世を客観的なものとみて、その中で�-
�立的に生きていこうとする近代的な人間観�-
�もない。ジゼルが主張する「個人的な主体�-
�としての人間は、この世の内部にすでにあ�-
�、この世の中において毎瞬間戦って実存的�-
�生きていく存在である。ジゼルが語る個人�-
�な主体は、この過程を通じて主体性を持つ�-
�人として生まれ変わる。そして、この世の�-
�部にすでにある、様々な象徴体系を自らの�-
�り方で再び象徴化する過程を通じて、個人�-
�な主体として生まれ変わる。ジゼルが提案�-
�る個人的な主体は、この世において困難を�-
�服しながら、まずは神を象徴化し、続いて�-
�の世を象徴化し、最後に人間自身を象徴化�-
�る過程を経るのである。ここでジゼルが語�-
�この世は、生物学的空間であり、同時に人�-
�のあらゆる欲望が満ち溢れている空間であ�-
�。この世は、人間間の葛藤と戦いが発生す�-
�ところであり、同時に新しい生命と新しい�-
�能性が現れる場所でもある。
この世において発生する葛藤や緊張、そ�-
�て限界とその克服を通じて、各人間は、そ�-
�ぞれ独自の内面の世界を作っていく。「個�-
�的な主体」は、このような一連の過程を通�-
�て、自然的存在としての人間から、「個人�-
�な主体」を持つ人間に生まれ変わるのであ�-
�。
ジゼルが語る主体としての人間観は、個�-
�としての主体である。近代の社会が作った�-
�治的集団的なイデオロギーに埋没していな�-
�個人的な立場を持つ主体である。ジゼルは�-
�個人を喪失させて集団に埋没させて生きる�-
�団的な人間観を批判する。そのうえでジゼ�-
�は、そっと個人を弱めて、社会の集団化を�-
�化する全体主義的な世界観についても批判�-
�る。つまり、個々人の独自性や特有性を生�-
�すのではなく、社会のすべての構成員を一�-
�のイデオロギーや一つの理念の下に集めよ�-
�とする同質性の世界観を批判しているので�-
�る。
「個人的な主体」とは、どういうものな�-
�であろうか。自らの主体だけを考えるので�-
�なく、他の人のことも考え配慮する存在で�-
�る。これは個人的な主体が、共同体の中で�-
�者とともに生きていくべき存在であること�-
�意味する。「個人的な主体」は、この世に�-
�いて一人暮らすのではなく、他人と共に生�-
�るべき運命に置かれている。
ジゼルの「個人的な主体」の概念は、極�-
�アジアにおいて、新たな社会を夢見て、新�-
�な主体論や新たな人間観を構築しようとし�-
�いる研究者にも、新たな「個人的な主体」�-
�いう概念の到来をどう図っていくか、多く�-
�インスピレーションを与えられよう。 7�-
��キリスト教の中心人物、イエス・キリスト<-
br /> 本書ではイエスは、人間の歴史において�-
�数多くのイメージを生み出した人物として�-
�介されている。イエスというユダヤの若者�-
�、キリスト教の歴史において、人間とは、�-
�とは何者なのか、多くのことを考えさせて�-
�た。
まず、キリスト教の信仰の歴史から見る�-
�、イエスは「単に人間であるだけだ」と、�-
�ゼルは主張する。人間イエスは、イエスに�-
�き従い、神の真理と人間の真理について思�-
�していた人びとに、この地上でどう生きて�-
�くか、考えさせたのである。このためジゼ�-
�は、イエスをキリストと告白し神学的に思�-
�するときには、人間イエスを歴史の脈絡か�-
�完全に切り離すのではなく、イエスが属し�-
�いた歴史の脈絡の中で思惟することを勧め�-
�。イエスは、ある日、天から降ってきた隕�-
�のような存在ではない。人間イエスは周り�-
�多くの人びとと同じ時代を呼吸し共に暮ら�-
�た。新約聖書では、イエスの周りにいた弟�-
�たちや、イエスにつき従った数多くの人び�-
�が紹介されている。そしてまた、イエスの�-
�は、パレスチナ地域を超えて中東各地で、�-
�多くの人びとによって口伝えで拡散され、�-
�リスト教という宗教の中心人物として紹介�-
�れた。この過程を経てイエスの話は、人び�-
�に人間が考える真理や、神が語る真理とは�-
�なのか考えさせるきっかけとなった。この�-
�エスの話を通じて、人びとは自分たちの過�-
�の経験について再考させられ、また未来へ�-
�新しい夢を見はじめた。このような過去と�-
�来への思惟を通じて、人びとは自分たちが�-
�きる意味を再考させられるようになった。�-
�間は律法と安息日のために存在するのでは�-
�く、律法と安息日は人間のためにあるとい�-
�宣言を聞いて、人間は自らの人生の意味を�-
�考するようになったのである。
以上のように、イエスのメッセージやイ�-
�スの人生の一部分だけに焦点を合わせて理�-
�するべきではない。イエスについて論じる�-
�ら、人間の歴史全体の過程の中で捉えなお�-
�べきなのである。さらには、イエスが来る�-
�、すなわち生まれる前に、ユダヤの宗教や�-
�化に何があったのかについても考えるべき�-
�あろう。そしてイエスが生きていたときに�-
�誰と一緒に過ごしたのか、イエスが死んだ�-
�、イエスの人生と死に関してどのような解�-
�が発生したのかを全体的に見てみなければ�-
�らないとジゼルは主張する。これが、ピエ�-
�ル・ジゼルが主張する「人間の歴史の中心�-
�物としてのイエス・キリスト論」である(�-
�二一頁)。
そのため、イエス・キリストは、神と人�-
�の間に位置する独特の「中間媒介者」では�-
�く、人間とは何者なのか、そして神とは何�-
�なのかという質問をさせる「媒介」として�-
�用するというのである。ジゼルが関心を持�-
�イエス・キリストのイメージは、純然たる�-
�間としてのイエスなのである。イエスは、�-
�リストとして、今日世俗化されたこの世に�-
�いても、ふたたび人間について、そして神�-
�ついて、考えさせる契機として作用する存�-
�なのである。つまり、イエスは、人間や神�-
�ついて思惟するための「媒介の役割」をす�-
�もので、人間イエスについての神学的思惟�-
�深めることで、人間は今日の新たな社会に�-
�するビジョンを作ることができるのである�-
�さらには同様に、すべての個人が自分たち�-
�独自性と唯一性を確保しつつ、共に豊かに�-
�らせる社会、多様性が保障される社会、多�-
�な価値観が尊重される社会という新たなビ�-
�ョンを想像することができると、ジゼルは�-
�張している。
8 個別者たちの抵抗と普遍性の陥穽。
��行われたピエール・ジゼルの引退記念講演�-
��の講演録がある。タイトルは、「個別者の�-
��抗と普遍性の陥穽――体と伝統、そして境�-
��の転覆の方法」である。
ジゼルが、この講演でいう「個別者」と�-
�、各宗教の伝統のことでもあり、人間各個�-
�のことでもある。また、ジゼルがいう「普�-
�性の陥穽」とは、それぞれの個別者が自分�-
�ちの独自性や特異性、唯一性を無視し、皆�-
�同質の世界に陥らせることを意味する。一�-
�の個別者の世界観を、すべての人に適用し�-
�うと強要することの暴力性を、ジゼルは問�-
�うとしているのである。すべての個別者に�-
�つの論理、一つの原理を強要することや、�-
�れを正当化する全体主義的な論理を建てる�-
�とを、ジゼルは「普遍性の陥穽」だという�-
�である。
ジゼルは以上のように「普遍性の陥穽」�-
�批判する。そして、その対案として出す普�-
�性の概念は、それぞれの個別者が自らの独�-
�性や唯一性、特異性が保障されるなかで、�-
�べての他者と共に生きていけることを保障�-
�る普遍性である(二三五~二三九頁)。
副題についても説明が必要であろう。ジ�-
�ルがいう「体」とは、一義的には人間が持�-
�肉体としての体である。ジゼルは、これを�-
�張適用し、制度的な機関をも体と称してい�-
�。
また、「伝統」とは、ユダヤ教、キリス�-
�教、そしてイスラム教のような唯一神教の�-
�教の伝統だけでなく、儒教や仏教、そして�-
�ンドのヒンズー教のような既存の大宗教を�-
�じめ、現在発生している数多くの新興宗教�-
�伝統、さらには数多くの文化の伝統を指す�-
�
そして、「境界」とは、宗教と宗教の間�-
�境界、文化と文化の間の境界を指す。
これら「体」「伝統」「境界」の内部で�-
�こる転換を指して、ジゼルは、「体と伝統�-
�そして境界の転覆」というのである。
4章で構成されたこの引退記念講演録で、�-
��ゼルは、再構成・再編成されつつある宗教�-
��現状について分析したうえで、近代が発展�-
��せた普遍性論争の中に隠されている「同一�-
��の論理」が宗教の伝統や人間論に適用され�-
��場合、どのように暴力的に作用するのかを�-
��察する。人間も、宗教や文化の伝統も、「�-
��数性」「多様性」に基づいていると見て、�-
��個別者の「独自性」「唯一性」「特異性」�-
��保障される普遍性の論理の啓発に多くの紙�-
��を割いている。
この引退記念講演録で注目すべきは、神�-
�と宗教学の違いが、どこにあるかを説明し�-
�いる部分である(二四七頁)。
これによると、神学とは、独自の固有の�-
�究の領域を持っている分科としての神学で�-
�なく、近代以降形成された多様な分科を横�-
�(transversal)して、神の真理とは何なのか、そ�-
��て人間の真理とは何なのかを問う「質問の�-
��態」であるという。
これに対し、近代以後形成された宗教学�-
�、宗教というのは何なのかという問を立て�-
�際、社会学、歴史学、心理学、そして人類�-
�など、近代以後発展した多様な方法を用い�-
�「回折関係」を通じて、質問への答えを求�-
�ていくだけのものであるという。 回折関係-
とは、それぞれの分科がぶつかった時に生じ-
る違いや共通点に基づいて、自らの学問的ア-
イデンティティを作っていく方法を意味する-
。これは、客観的そして中立的態度を堅持し-
ながら、宗教についての質問を続ける学問的-
態度であるともいえよう。このような宗教学-
の方法論をジゼルは、平面的なレベルの研究-
であるとして批判している。
9 まとめ
本書は、内在主義的な世界観から発展し�-
�きた東北アジアのキリスト教を研究する者�-
�、「神」と「この世」そして「人間」に対�-
�る新しい問いかけをさせる良書である。
第一に、ピエール・ジゼルの神学が、超�-
�的神についての批判と見直しの中で形成さ�-
�た西欧の現代神学であるという点で、アジ�-
�の研究者が神学的思惟をする際に、新たな�-
�点を提供するといえよう。
ピエール・ジゼルの神学は、神を過度に�-
�きな存在と意識した西洋の神学を批判し、�-
�時に人間の可能性に対して過剰な期待を抱�-
�ていた西洋近代の哲学を批判する中で、新�-
�な道を見つけた神学といえる。これは固有�-
�神学的な談論においてだけでなく、現在の�-
�教学や宗教哲学に対する批判と検討を通じ�-
�、ジゼルは新たな神学の可能性を探求して�-
�る。
また、「エクセ」という新しい概念を通�-
�て、新たな神のイメージを提案しようとし�-
�点で、ジゼルの神学的思惟は、アジアの研�-
�者にとって意味があろう。しかしながら、�-
�のようなジゼルの神についての理解は、近�-
�以後に形成・発展してきた超越論的神に対�-
�る批判の中から生まれたものであるため、�-
�ジアの研究者たちは次のような疑問を抱く�-
�あろう。内在主義的な世界観の中で発展し�-
�きたアジアの思想の土壌においては、いか�-
�して神についての新たな想像ができるのだ�-
�うか。これはアジアの神学界における論点�-
�して、注目すべきものである。
つぎに、本書はアジア人も生きている場�-
�ある自然について、新たな質問を可能にし�-
�う。近代西洋において発展した自然観で言�-
�れているように、自然をエコシステムと見�-
�のではなく、あらゆるものの根源としての�-
�然理解は、どのようなものであろうか。人�-
�が管理すべき環境としての自然ではなく、�-
�べての生命の根源としての自然という観点�-
�らは、ジゼルのいう「この世」は狭い意味�-
�の人間の社会生活の場だけを意味するので�-
�という批判が起ころう。この世は、人間の�-
�界だけでなく、生命が展開する場としての�-
�の世でなければならない。
これらのジゼルの論からは、今後アジア�-
�展開していく神学は、狭い意味での人間中�-
�主義に基づくものではなく、より幅広い意�-
�で生命が展開する場としてのこの世を神学�-
�思惟の場にすべきであるという示唆が得ら�-
�よう。
最後に、本書は、アジアで神学的思惟を�-
�開しようとする研究者に、どのような新し�-
�人間観を提案できるのか考えさせてくれる�-
�この世で自己実現することによって主体と�-
�るというジゼルの個人的主体論が持つ人間�-
�は、自然の一部として埋没する人間観では�-
�い。だからといって、この世を克服する過�-
�の中では、自然を破壊せざるを得ないと、�-
�明する人間観でもない。ジゼルの個人的主�-
�論は、こうした既存のビジョンとは異なり�-
�第三の道を想起させるものである。そのた�-
�個人的主体論は、人間中心的世界観が引き�-
�こした自然破壊を省察する際にも、有用な�-
�論的道具となりうる。集団主義的世界観に�-
�収されずに、主体としての個人として生き�-
�いく道は、どのようにすれば可能になるの�-
�、ジゼルの個人的主体論がアジアの研究者�-
�問いかけている。
ピエール・ジゼル
スイス・ローザンヌ国立大学宗教神学部�-
�誉教授。『抵抗と克服のあいだの人間』(�-
�訳)をはじめとする40冊あまりの著書や論文-
を発表している。宗教学と宗教哲学、そして-
現代の多様な宗教とキリスト教神学の対照な-
どをテーマに研究を続けている。
韓 亨模(ハン ヒョンモ)
日本基督教団丹後宮津主任担任牧師。京�-
�在住。
著書に『Déconstruction d’une image de Jésus, l’Historicité et la Nature: Réflexion à l’horizon d’une confrontation Orient-Occident sur fond de postmodernité(イエスのイメージの解体、歴史�-
��そして自然――近代後期性における東洋西�-
��の対面の地平についての思惟)) 』(フランスの出版社L’Harmattan,Paris, 2014年)(未訳)がある。論文に「세 유형의 철학적 신:폴 리꾀르, 타나베 하지메 그리고 양명수의 경우(三類型の哲学的神:ポール・リクール�-
�田邊元そしてヤン・ミョンスの場合)」(�-
�神学思想)No.165)などがある。
Moteur de recherche www.editions-beauchesne.com
Le moteur peut rechercher dans différents champs :
- Un nom d’auteur (AUTEUR)
- Un mot du titre (TITRE)
- Un ISBN
- Un mot du texte de présentation (TEXTE)
- Un mot du sommaire ou de la table des matières (SOMMAIRE).
La recherche dans les champs TEXTE et SOMMAIRE peut être un peu longue.
En cliquant sur un resultat la fiche du livre correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet.
Search engine www.editions-beauchesne.com
The engine can search in different fields:
- An author's name (AUTEUR)
- A word from the title (TITRE)
- An ISBN
- A word from the presentation text (TEXTE)
- A word from the summary or the table of contents (SOMMAIRE).
The search in the TEXTE and SOMMAIRE fields may take some time.
Clicking on a result open the book's sheet in a new tab.